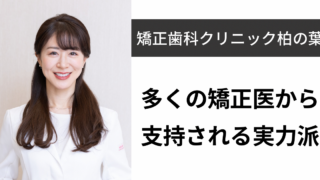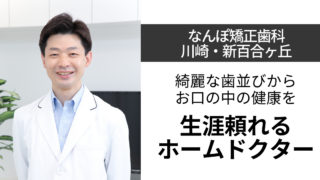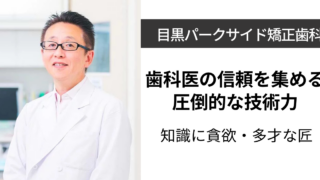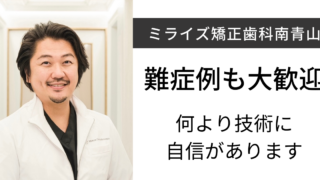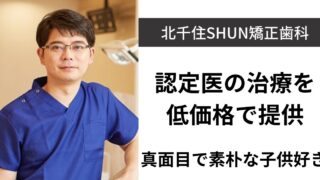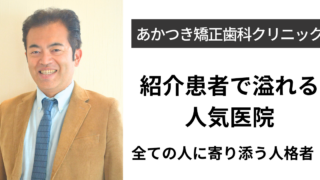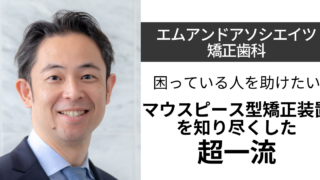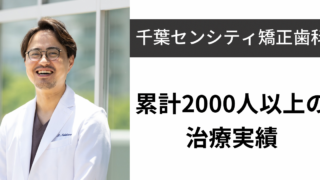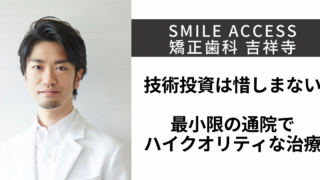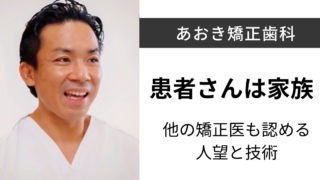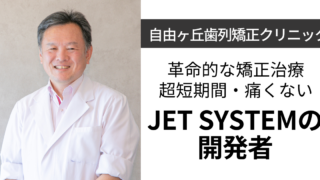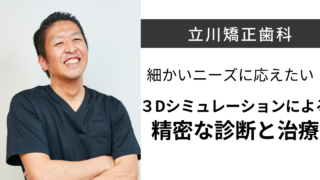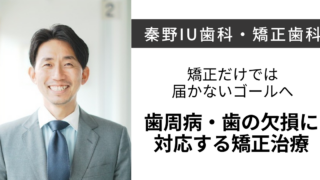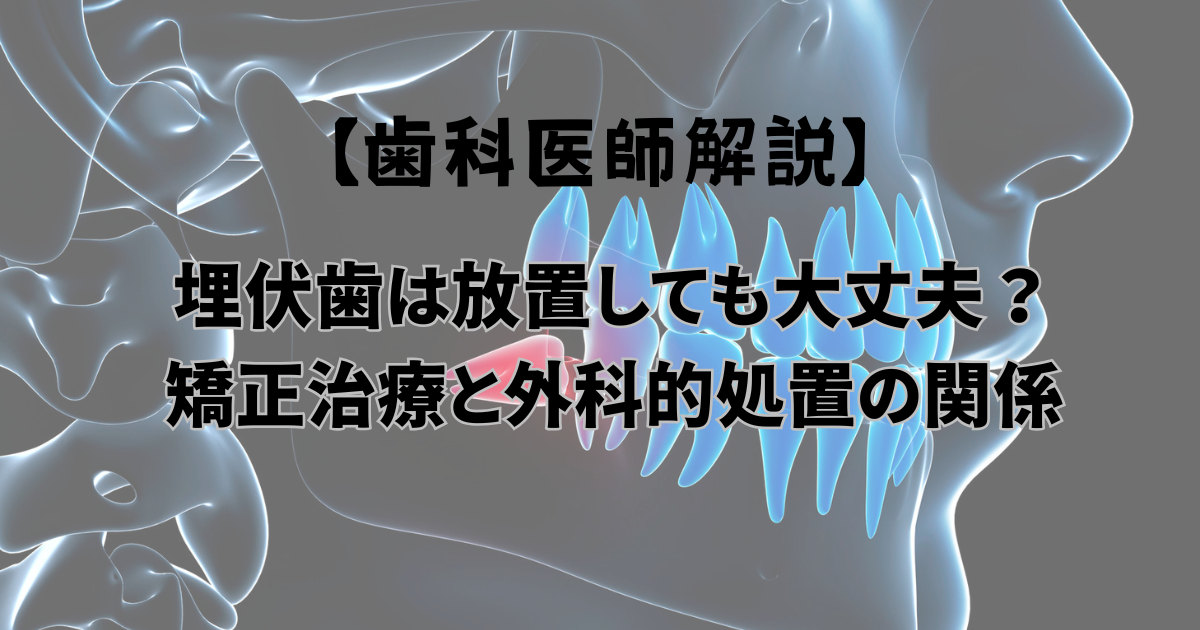
埋伏歯は放置しても大丈夫?矯正治療と外科的処置の関係
埋伏歯は直接的に痛みを生じたりすることは稀ですが、埋伏歯が原因で、萌出障害、嚢胞や炎症といった様々な問題を起こすことがあります。埋伏歯がある場合は、存在する場所や影響をよく考慮し、抜歯を含めた治療をするか否かを決めていきます。また、矯正治療する際も埋伏歯の存在は重要になってきます。埋伏歯を歯列に組み込んで並べる場合もあるため、すべての埋伏歯に存在意義がないわけではありません。
①埋伏歯とは?|原因や見つかるタイミング

埋伏歯は骨や歯肉の中に埋まっている歯のことを指します。よく埋伏歯が発見される部位は、親知らず・犬歯(前から3番目の歯)・小臼歯(前から4番目か5番目の歯)です。
なぜ埋伏になるかは様々な理由がありますが、顎の骨の成長が悪く、顎が小さい場合や、周りの歯や、骨の中の腫瘍や膿疱などの影響で、萌出阻害が起きていることが主な理由です。レントゲンや矯正相談時に初めて見つかるケースが多いです。
②埋伏歯を放置するとどうなる?|放置リスクと将来的な問題

埋伏歯を放置すると、ケースによっては隣接歯の歯根吸収・歯列不正の原因となることがあります。隣接歯の歯根吸収に関しては、埋伏歯が萌出しようとする力がかかる先に隣接歯の歯根が存在すると、起こり得ることがあります。
埋伏歯の歯根が未完成の場合に萌出する力が出ることが多いので、歯根が完成していない埋伏歯の歯冠の先に隣在歯の歯根や歯冠がある場合は、注意が必要です。歯列不正に関しては、埋伏歯が存在すると隣在歯の正常な萌出を阻害することがあります。この場合は早めに埋伏歯を抜歯する必要があります。埋伏歯の歯根が完成しており、他の歯や矯正治療に影響がない場合は、そのまま放置しても大丈夫なこともあります。
嚢胞や炎症を伴う場合
嚢胞とは簡単にいうと膿の袋のことをいいますが、埋伏歯がある場合、埋伏歯の周りに嚢胞や炎症が起こる可能性があります。埋伏歯は通常歯が存在しない骨の中にあるので、何らかの原因で炎症が起こったとしても、正常な創傷治癒が働かないことがあります。
これにより、嚢胞の形成やながびく炎症を助長することがあります。基本的に埋伏歯に嚢胞や炎症が起きた場合は、その嚢胞や炎症ごと埋伏歯を抜歯することをお勧めします。放置すると嚢胞や炎症が大きくなり、顎骨の骨折や、最悪の場合命の危険を及ぼすことがあります。
矯正治療を行う際に支障が出る場合
矯正治療は骨の中で歯を動かすため、動かしたい方向に埋伏歯があると、矯正治療の邪魔になります。よってCT等で矯正治療の邪魔になると判断された場合は、矯正治療前に抜歯の対象となります。放置して矯正治療を開始した場合、動かしたい方向に邪魔な歯が存在するため、矯正治療がうまくいかないことがあります。
③矯正治療と埋伏歯の関係
矯正治療を計画するうえで、埋伏歯の有無は重要です。その埋伏歯を活かせるのか活かせないかのまずは判断になります。生かす場合は、開窓牽引(かいそうけんいん)という歯肉を切り、埋伏歯を剥き出しにして、矯正力でひっぱり、正しい位置への誘導を試みます。活かせない場合は、抜歯となります。いずれにしても、歯並び・かみ合わせ全体を見て治療計画を立てる必要があります。
④埋伏歯の外科的処置とは?|口腔外科の役割

開窓術とは?
開窓術とは、歯肉をメスやレーザーで切り、埋伏歯を剥き出しにして萌出を促す治療法です。基本的には骨から埋伏歯は出ているが、歯肉に覆われている場合や、骨の中にはあるが比較的浅い位置に埋伏している場合が対象となります。骨の中にある場合は、骨を削らなければならないので、治療後に痛み腫れが出ることが多いです。
牽引処置の流れ
開窓した後に、矯正力によって正しい位置に埋伏歯を持ってくることを牽引といいます。よく行う手段としては、開窓した埋伏歯に金属やプラスチックのボタンを付与し、そこにゴムやワイヤーを引っ掛けて埋伏歯を引っ張るという治療が行われます。当然引っ張るためには、引っ張る側の固定源が必要となるため、マルチブラケット装置や、矯正用のアンカーインプラントが利用されることが多いです。牽引がうまくいかない場合は、歯根と骨が癒着していることがあるので、その場合は抜歯を検討することもあります。
抜歯の判断になるケース
埋伏歯の位置関係により、残念ながら抜歯の適応となる場合があります。特に過剰歯の場合は抜歯になるケースが多いです。埋伏歯を抜歯する際は、顎の骨の太い血管や神経に注意しながら抜歯しなければなりません。場合によっては全身麻酔での抜歯を考えなければならないこともあります。埋伏歯の抜歯をする場合は、担当医からよくリスクを聞き、理解することが大切です。
⑤外科処置が必要になるかどうかの判断基準
埋伏歯を抜歯したり、開窓したりする場合は、麻酔や切開といった外科処置が必要となります。抜歯に関しては、例えば年齢が低いと治療への協力度が低く、先に述べたように全身麻酔の適応になります。全身麻酔も全くリスクがあるわけではないため、緊急性と埋伏位置・方向・周囲骨の状態などを考慮し、いつ処置を行うか否かが決定されます。もちろんその際に、CT撮影や精密検査による診断が重要なのはいうまでもありません。正確な診断の上で治療計画が立案されないと、抜歯に非常に時間がかかってしまい、患者さんの負担も大きくなってきます。
開窓は抜歯ほどリスクの高い処置ではありませんが、やはり患者さんの協力度が低いと難しい処置になります。抜歯同様に、さまざまな要素を加味して実施時期が検討されるでしょう。開窓の場合は、処置後に歯に汚れが付きやすいので、処置後のセルフコントロールに協力的な姿勢も必要になってきます。
⑥まとめ|早期発見とチーム医療がカギ
埋伏歯は放置せず、お通いの歯科医院や専門医による早期の診断が大切です。埋伏歯は基本症状がないことが多いので、早めの診察をお勧めします。特に矯正治療をお考えであれば、矯正医と口腔外科医の連携がとれた医療機関を受診することをお勧めします。自分が納得いくまで説明を受けてから治療を開始するようにしましょう。
 執筆 歯科医師/issy
執筆 歯科医師/issy
国立歯学部卒業後、東京医科歯科大学歯学部附属病院で研修、現在勤務医として一般歯科、矯正歯科に携わっている。日本口腔インプラント学会所属